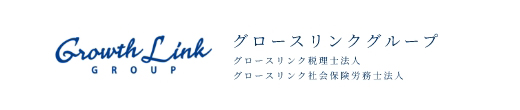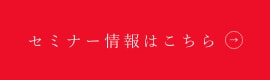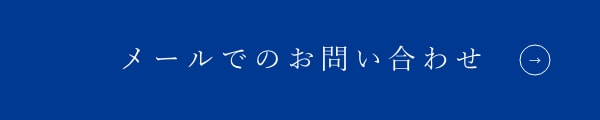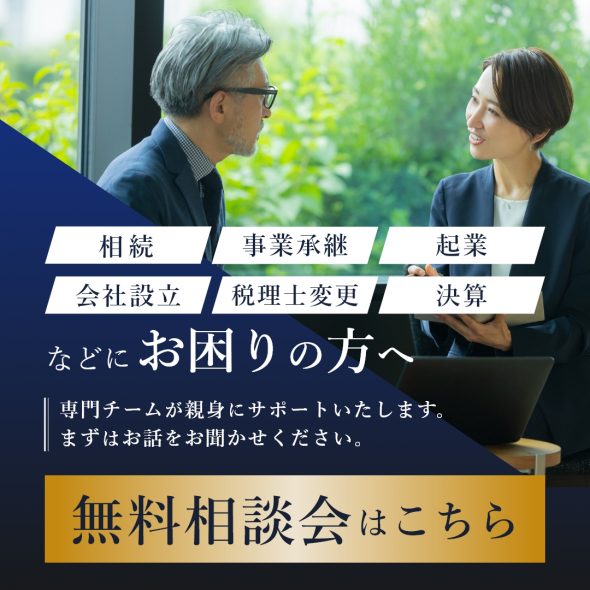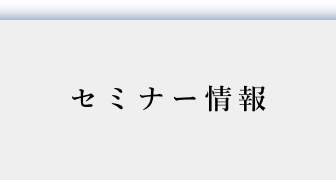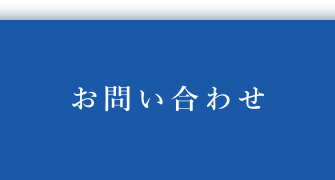税務
2025/07/08
名古屋の税理士コラム|「M&A」は特別な話じゃない!中小企業が活用すべき事業承継の選択肢と税務のポイント

名古屋の税理士、グロースリンク税理士法人
中小企業の経営者の皆様、貴社の事業の未来について、漠然とした不安を抱えていませんか? 特に、親族内に後継者がいない、従業員への承継も難しいといった場合、「この会社、この技術、この雇用をどう守っていくか」という課題は、多くの経営者の頭を悩ませる深刻な問題です。
そんな時にぜひ検討していただきたいのが、もはや大企業だけの話ではない「M&A」、特に「事業承継型M&A」です。
なぜ今、「M&A」が経営者の間で注目されるのか?
M&Aというと、映画に出てくるような大企業の買収劇を想像されるかもしれませんが、現代においては、中小企業が事業を存続させ、成長させるための現実的な選択肢として広く認識され始めています。その背景には、以下のような理由があります。
-
深刻な後継者不足の解消: 日本の中小企業の約3分の2が後継者不在と言われています。廃業を選ぶ前に、外部の企業に事業を引き継いでもらうM&Aは、雇用を守り、培ってきた技術やノウハウを次世代に繋ぐ有効な手段となります。
-
事業の成長・拡大の加速: 譲渡側にとっては、買い手企業の資金力や販路、人材、ノウハウなどを活用することで、自社単独では難しかった事業の成長やスケールアップを実現できる可能性があります。
-
創業者利益の獲得とリタイアの実現: 長年育ててきた会社を売却することで、経営者はまとまった創業者利益を得て、引退後の資金を確保できます。また、自身の理想とするタイミングでのリタイアを計画的に進めることが可能になります。
-
関係する税制優遇措置の活用: 事業承継を目的としたM&Aには、国が設けている税制優遇措置(事業承継税制など)が適用される可能性があります。これらを活用することで、M&Aに伴う税負担を大幅に軽減できる場合があります。
M&Aを検討する際に経営者が知るべき税務のポイント
M&Aは、会社の売却や買収という大きな決断です。特に、税金に関する知識なしに進めると思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
-
譲渡スキームによる課税関係の違い: M&Aには、「株式譲渡」「事業譲渡」「会社分割」など、複数のスキーム(手法)があります。どのスキームを選択するかによって、売却益にかかる税金の種類や税率、納税義務者(個人か法人か)が大きく異なります。ご自身の状況や目的に合った最適なスキームを検討することが非常に重要です。
-
譲渡所得の税率と節税対策: 個人が株式を譲渡した場合の利益(譲渡所得)には、通常、所得税・住民税・復興特別所得税を合わせて約20%の税金がかかります。しかし、事業承継税制など、特定の要件を満たすことで、税負担を軽減できる可能性があります。
-
企業の適切な価値評価(バリュエーション): 会社の売却価格は、最終的に買い手との交渉で決まりますが、そのベースとなるのが会社の価値評価です。この評価が適切でないと、本来得られるはずの利益を逃したり、税務上の問題が生じたりする可能性があります。税務的な視点も踏まえた客観的な価値評価が重要です。
-
M&Aにかかる諸費用と税務上の取扱い: M&Aには、仲介手数料、デューデリジェンス費用(企業監査費用)、弁護士費用など、様々な費用が発生します。これらの費用が税務上、損金として認められるか否かも重要なポイントです。
まとめ:M&Aは「次世代への架け橋」
M&Aは、単に会社を売る、買うといった行為に留まりません。それは、経営者が長年築き上げてきた事業や、そこで働く従業員の未来を考え、「次世代への架け橋」を築く重要な経営判断です。
しかし、そのプロセスは複雑で、法務、財務、税務など多岐にわたる専門知識が必要です。特に、税務戦略を誤ると、せっかくのM&Aのメリットが半減してしまう可能性もありますので、是非ご相談ください!
その他、ご不明な点があれば
名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!